永楽和全の茶道具買取について
藝品館では永楽和全(永樂和全)作品の茶道具の買取査定を行っております。
永楽和全の茶碗・香合・水指・茶器等、京焼・茶道具の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。
経験豊富なスタッフや茶道具の専門家が責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
他の永楽善五郎作品、また作家作品の茶道具の買取も行っております。
永楽和全とは
永楽和全(えいらくわぜん)文政6年-明治29年(1823-1896)は、幕末明治の京焼の陶工で、十二代永楽善五郎です。
若い頃から父・永楽保全をうならせる陶技を発揮した和全は、幕末明治の激動の時代を生きました。焼物の研究に熱心なあまり多額の借金を重ねた父の後を継ぎ、家を維持することに力を注ぎ、義弟とともに立て直しました。
幕末に仁清ゆかりの地で登窯(御室窯)を持ち、維新を迎えてからは京都を離れて加賀山代の「九谷釜」で陶技の指導し、さらには裏千家十一代玄々斎の高弟・鈴木利蔵に招かれ三河岡崎に窯を作って従事しました。また、明治になってから始まった神社仏閣での献茶や大寄せの茶会用として、華やかな茶道具一式を生み出し、新しい永楽家の茶陶の様式を確立しました。
永楽和全は、金襴手の優品を多く残していることでも知られています。
永楽和全の生い立ち
永楽和全は、保全の長男として文政6年(1823)に生まれ、幼名を仙太郎といいました。
天保14年(1843)、父・保全の隠居をともない、弱冠21歳にして十二代善五郎を襲名しました。和全の善五郎時代は、明治4年(1871)に家督を長男の常次郎(得全)に譲って自らを善一郎と称するまでの約28年間です。 和全は、25歳のときに酒造業を営んでいた木屋久兵衛の娘古宇を妻に迎えています。
永楽和全の作風
永楽和全の作風は父・保全の作風に比べてどこか鷹揚な雰囲気があり、写し物は本歌を踏まえつつもやや崩して写す傾向があるため、茶人の間では和全のわびて茶味のある作品の方が評価が高いとされています。
これは、波乱の時代を生き経済的な苦労を重ねた和全が至った、わびの境地の深さをあらわしているともいわれています。
嘉永元年頃、鷹司家の注文で近衛家に秘蔵される「揚名爐」の写しの制作で和全は保全の手伝いにあたり、このとき保全を感嘆させる陶才を示したと伝えられています。しかしこの頃から、相続のことで保全との関係に不和が生じています。
この頃まで和全の作陶生活は、西村家の当主として京都市内でそれまでと同じように小規模な工房体制で生産を続けていましたが、嘉永5年頃になると、義弟宗三郎とともに御室仁和寺門前の仁清窯跡に窯を築き、このころから和全の本格的な作陶活動が始まったと言われています。
永楽和全の作陶活動を大きく分けると、この「御室窯」時代、慶応2年(1866)から明治3年(1870)にかけて加賀大聖寺藩に招かれて山代で製陶の指導に当たった「九谷釜」時代、明治5年から明治10年にわたって三河岡崎の豪商鈴木利蔵に招かれて作陶した「岡崎窯」時代と帰京時代、明治15年(1882)に油小路一条の住まいを売り払い東山の下河原鷲尾町に移って窯を築いた「菊谷窯」時代と、以上の4つの制作期に分けることができます。
「御室窯」時代と「善五郎」共箱作品
御室窯は嘉永6年に開窯したと言われています。御室の窯は、義弟宗三郎の所有地に築いたと伝えられています。
その地が仁清の窯跡であったことは窯を築く際に仁清印のある陶片がその地で出土したことからわかったそうです。しかし、開窯に当たっては、郊外における永楽家自前の本釜所有の実現、仁清以来衰退していた御室窯の復興、仁和寺の御用窯的な展開など、いくつかの目論見があっての開窯であったようです。
また、御室での開窯には、宗三郎の存在が必要不可欠であったと考えられ、和全との緊密な協力体制がなければ実現しませんでした。
この窯では金襴手や色絵など、当初から完成度の高い作品が焼かれていましたが、このような時期的に早い段階から様々な技法の作品が作られ、かつ完成度が高いのは、永楽和全の卓越した陶技のみならず、義弟宗三郎をはじめ轆轤師西山藤助などの熟練した職人も加わった工房体制があったためと考えられています。
この時期の作風としては、金襴手と色絵の懐石用高級食器が作られ、仁清・乾山の色絵磁器を強く意識した作陶がなされています。
御室窯が開窯した嘉永6年は、ペリーが浦賀に来航した年でした。保全が翌嘉永7年に亡くなり、多額の負債を残し、和全はその負債を抱えて明治維新の動乱を乗り越えなければなりませんでした。
「九谷窯」時代と善一郎時代
慶応2年(1866)頃、加賀大聖寺藩から九谷焼の技術指導のため招かれ、和全をはじめ宗三郎や常次郎(得全)ほか工房をあげて山代春日山に移り住み指導にあたります。これが、永楽和全の九谷窯時代です。
和全の指導によりその後の九谷焼に定着した技法が金襴手でありますが、保全の金襴手は金泥を用い、和全から金箔を使った金襴手が焼けるようになったとされ、山代では良質の金沢金箔を使った金襴手が焼かれたと伝えられています。
「岡崎窯」時代と帰京時代
明治に入ると、急激な西洋化で京都の伝統文化は軒並み没落の危機に瀕していました。永楽和全は明治3年(1870)に山代から京都に引き上げ、翌4年には隠居して長男常次郎(後の十四代善五郎・永楽得全)に家督を譲り、自らは善一郎を名乗ります。
またこのとき、西村姓を永楽姓に正式に改姓しています。
明治5年には、裏千家十一代玄々斎の高弟・鈴木利蔵の招きで三河岡崎に赴きます。
岡崎甲山での3年間にわたる作陶は、主に赤絵や染付など磁器の量産であったとされています。明治維新で時代が大きくかわり、茶道の世界も様相が大きく変わる中で、時代に応じた西洋的な作品(コーヒー碗やスープ皿など)の制作も手掛け、柔軟に作品を生み出していきました。
またこの間、明治6年には東京の三井家に出向き、和全製品の定期的購入を目的とする「永製講」を組織するなど、三井家の協力を仰ぐものの、実現には至りませんでした。その後、得全による大阪造幣寮の坩堝製作という三井関係の仕事に和全も関わるものの、不成功に終わり、経済的困窮はなかなか解決されませんでした。
しかし、その後明治10年に岡崎に見切りをつけて京都に帰り、帰京後は三井家との交流が深まり、三井家からの注文が増えていきました。
「菊谷窯」時代
和全は、明治15年(1882)に油小路一条から東山高台寺に近い下河原鷹尾町の菊渓川のほとりに住まいを移し、菊谷窯を開窯しています。
この頃妻を亡くし、耳が聾したと言われ、自ら「耳聾軒」と号しました。
菊谷焼は、粗い胎土に薄く透明釉を掛けて簡略な絵付けを施したものが多く、民芸風ともいえる風流な味わいがあり、晩年の永楽和全の境地が窺える作風です。この菊谷焼に捺される繭印「菊谷」の印文は、三井高福の書といわれ、菊谷窯には三井家が深く関与していたと考えられています。
また、明治20年(1887)年に京都御苑内で開かれていた京都博覧会の会場で、明治天皇への献茶に和全の天目茶碗が使われました。
この献茶は、三井高朗と三井高棟(北家十代、1857-1948)が主席となり、表千家碌々斎が点前を行っています。
さらにその席上、日の丸釜にまつわる御下問があり、それを記念して和全により日の丸茶碗がやかれています。さらに、明治23年に京都高等女学校で行われた皇后陛下への献茶でも和全の白地金襴手鳳凰文天目が用いられています。
この頃から日本文化を見直す気運が高まり、伝統文化の振興が図られましたが、それらの献茶はそういった背景を象徴する出来事でした。永楽和全は、そういった神社仏閣での献茶や大寄せの茶会用として、華やかな茶道具を生み出し、永楽家の新たな茶陶の様式を確立したのです。
明治29年(1896)、永楽和全は74歳で亡くなりました。
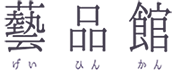

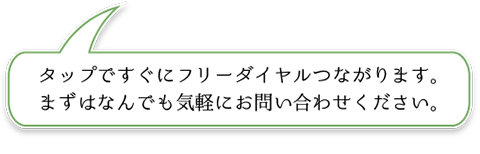
 LINEで
LINEで