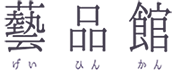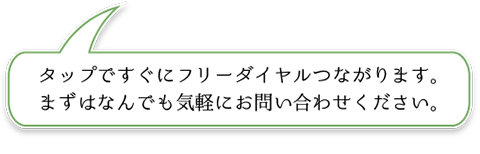岡山の掛け軸買取について
岡山の掛け軸買取は藝品館へおまかせ下さい。大切にされてきた掛け軸、お引き継ぎになられた掛け軸類を高価買取いたします。
出張査定は無料で対応させていただきます。遠方であっても、鑑定料など査定額が変わることはございませんのでご安心の上、お気軽にお申しつけいただければと思います。
古くて箱の状態がボロボロのもの、状態の悪いものでも問題ありません。掛け軸の買取はぜひ藝品館にお申し付けください。売買の個人情報は秘密を厳守し、お取引させていただいております。
公的機関や法人様、弁護士様・税理士様など士業の方からの相続等の美術品評価査定も承っております。
掛け軸は日本の伝統文化と深く結びついた美術品ですが、掛け軸を正確に査定評価するには専門の知識が不可欠です。岡山県で掛け軸の買取・査定鑑定を検討されている方は気軽にご相談ください。
またこちらのページでも掛け軸の買取に関する説明をさせていただいております。
掛け軸の買取について
掛け軸の買取における藝品館の強み
掛け軸の査定・鑑定
掛け軸はそのもの自体というよりも、書や絵画を描いたのが誰なのか?という点が一番重要となります。作者と時代によって大きく価格が変わります。
藝品館ではこれらの要素を詳細に調査し、最も最適な価格を算出します。
掛け軸がなぜその値段なのか
掛け軸がなぜその価格になるのか、藝品館の専門鑑定士が詳細に説明します。作者、時代背景、使用されている素材、技法、そして現在の市場価格等を総合的に考慮し、査定額を出します。
藝品館では専門の鑑定士がこれらの要素を誠心誠意、詳細に解説します。売買の具体例を参考資料にすることが可能な場合も多くあります。
高い専門性による評価と信頼
藝品館では長年の実績と専門性で、お客様から高い評価と信頼を得ています。全ての査定・鑑定作業は透明性を持って行い、お客様に安心してご利用いただけるよう心がけています。
破れていても、箱がなくても、その掛け軸には確かな価値があります。藝品館の専門の鑑定士がその価値をしっかりと評価し、高価買取を実施します。岡山県で掛け軸の買取・査定鑑定を考えているなら、ぜひ藝品館にお任せください。
破れていても、箱がなくても大丈夫です
掛け軸は繊細な作品であり、時間とともに破れたり、保存用の箱が失われたりすることもあります。しかし、藝品館ではそうした条件でも査定・鑑定を行い専門の鑑定士が丁寧にその価値を見極めます。
掛け軸は多くが書画骨董の部類に入り、中の絵画や書画がいつの時代の、どの作家によるものかを明らかにすることからはじめないといけません。作家や時代を明らかにすることで、江戸時代なら江戸時代の表具、紙質、仕立てがあり、狩野派なら狩野派の描き方などといった、その特徴と関連歴史書籍も調査して査定鑑定します。
岡山県の書画・掛け軸
岡山県では室町時代より様々な方向性の個性に富んだ作家が活動していました。時期やジャンルは異なれど岡山の土地はそれを許容するほどに豊かであり、雪舟の絵画をはじめ、浦上玉堂の書画、幕末には漢学者・山田方谷の書などが世に送り出されました。
このような豊かで活発な岡山のような土地では古い掛軸が見つかることがあります。なにか古いものを発見された際には、整理、鑑定、査定のご相談から承っておりますので、ぜひご連絡ください。
岡山を代表する画家
雪舟等楊
岡山出身で掛け軸などの作品を残した人物としては、第一に雪舟等楊が挙げられます。室町時代に京の相国寺や中国の明で絵画を学び、現在に至るまで日本の絵画に影響を与えています。岡山県立美術館(岡山市北区天神町8−48)には雪舟の 山水画(倣玉澗) (重要文化財)や、若描きとされる山水図 雪景山水図 、学問の神とされる菅原道真を唐服で描く 渡唐天神図 などが収められています。
宮本二天
戦国時代末期からは剣豪としても名高い、美作出身の 宮本武蔵が、剣士として活躍するかたわら「二天」の号をもちいて画業も行ないました。岡山県立美術館には濃墨で表された 鵜図 や竹に止まる雀を描いた 竹雀柳燕図 等、一瞬の物事を描く作品など5点が収められています。
浦上玉堂と浦上春琴
江戸時代半ばには浅口の地から浦上玉堂が輩出され、玉堂は大阪や京、江戸の文人たちと交流して書画を大量に描きました。多くの作品が岡山県立博物館(岡山市北区後楽園1−5)や岡山県立美術館に収蔵され、その大部分は掛け軸として残されています。特に県立美術館の名品として知られる 山高水長図 は脂ののった60代後半頃の作品とされ、右に偏重する猛々しい山岳が勇壮な作品です。
玉堂の子、 浦上春琴の作品も県立美術館に収蔵され 僊山清暁図 は洗練された描線と彩色を持ち、山や木々も非常に変化に富む作品です。
江戸時代岡山の四条派
江戸時代の末頃には岡山から柴田義董と岡本豊彦の2人が出て、京で活躍しました。京にいても岡山との交流は欠かすことなく続けられていて多くの作品が岡山に残り、また2人の門人には岡山出身の者も多くいました。岡山県立美術館には山水は豊彦とも謳われた豊彦の 林和靖図 があり、この作品は主役の高士・林和靖が画面の下部に小さく描かれ、その上に四条派らしい斜めに画面を横切る山々を描いており、豊彦の四条派としての実力がよく示されています。
岡山近代の画家
瀬戸内市からは大正に 竹久夢二が活躍しています。夢二は独特な世界観で作品を制作し、特に美人画は哀愁を帯びた理想の女性を描き「夢二式美人」と呼ばれます。夢二郷土美術館(岡山市中区浜2丁目1−32)には夢二の美人画を中心に、様々な掛け軸作品が収蔵されています。
笠松市立竹橋美術館では明治から昭和に活躍した、小野竹喬の作品が多数収められています。その中には掛け軸作品として製作された 島二作 が収められています。この作品はセザンヌなどの西洋画に影響を受けた明るい色彩と四条派の得意とする斜めに画面を横切る山々で画面が構成され、近代の新たな日本画として文展で特選を得ています。
岡山ゆかりの書
清巌正徹
清巌正徹は室町時代初期の1380年に、一族が祠官をしていた石清水八幡宮の知行所である小田郡に生まれた歌人です。京の冷泉為尹と今川了俊に和歌を学んだ後、出家し正徹と称しました。多くの和歌を詠み、約2万首もの歌が存在しています。京の東寺の書記をしていたため「徹書記」とも呼ばれました。藤原定家の作風に傾倒 正徹物語 を執筆し藤原定家の歌風をたたえて、東寺の保守的な二条派の歌壇の中に幽玄の風をもたらしました。
歌人だけでなく書家としても名手とされ、歌と同じく藤原定家の書に学び、書の風体の開拓をしています。今でも正徹の作品は古筆、歌切、茶掛けとして出てくることがあります。
室町時代の書状
室町時代半ばには戦国時代が始まり、多くの地で政治や軍事が混乱しました。戦国時代力を持った人物は、自分の領土としたところに様々な書状で、政策や寺社の保護などの命を下しました。他にも外の権力者との交流や、幕府からの書状なども活発にやり取りされました。
このような書状や書簡、消息などは、茶掛けとして掛け軸にされていることも多く、岡山では三村家との戦闘の様子が記されている 宇喜多直家書状 などが掛け軸として使用されました。
山田方谷
山田方谷は1805年に現在の高梁市で生まれ、幼くして神童と呼ばれるほど学問に優れていました。朱子学を学び、ついで陽明学を修めて陽明学者となります。松山藩主板倉氏から藩校・有終館の学頭に任命されます。1849年藩主板倉氏に招聘され、藩の財政改革を行い、殖産を奨励し藩を救いました。松山藩の老中ともなり異例の出世を遂げました。また私塾を開いて学問を広めることも精力的に行っており多くの門人を迎え入れています。明治維新で板倉氏の再興に奔走しながら塾を続け、また藩の学校であった閑谷学校でも陽明学の講義を行ないました。
多くの漢書、漢詩の作品が残り、文書や掛け軸として書が製作されています。
緒方洪庵
緒方洪庵は幕末1810年に備中足守藩の藩士の家に生まれた医師、蘭学者です。大阪で医学と蘭学を学び、その後蘭学の塾「適塾」を開いています。コレラや天然痘の防除に多大な功績があり、幕府からも奥医師として招かれます。洪庵の開いた適塾からは福澤諭吉、大村益次郎などのちの日本を導く人物が幾人も出ています。
緒方洪庵の書は多く残っており、医師、蘭学者としての戒めを記するものがあります。また和歌なども嗜んだので、短冊の作品なども残されています。
阪谷朗廬
阪谷朗廬は1822年に現在の井原市の地で生まれました。父について大阪へ行き、大塩平八郎の下で学問を修めます。また父の異動で江戸に上京し、朱子学である昌谷碩や古賀侗庵について朱子学を学びました。その後帰郷し、地元で桜渓塾を開き学問を教えています。1853年にはその学識を認められ、一橋徳川氏が創設した学校である興譲館の初代館長を務めます。明治維新後は福沢諭吉らと共に啓蒙学術団体である明六社に参加し、明治維新後の地方の学問、学校について大きな功績を残しました。
多くの著作が残っていますが、書の作品もあり儒学者らしい漢書の引用や漢詩の掛け軸などが残っています。
犬養木堂
犬養毅は幕末の1855年現在の岡山市で大庄屋の子として生まれました。故郷で漢学を修めた後、東京で慶應義塾に入り、新聞記者となりました。その後選挙に出て連戦連勝し、逓信(郵便)大臣となり、総理大臣に立てられます。
書、漢詩に秀でており木堂という号で、全国各地に作品を残しています。また故郷岡山の自宅は現在、犬養木堂記念館(岡山市北区川入102−1)となっており建物自体が国の重要文化財となり、ゆかりの品を展示しています。漢詩や激励の手紙が掛け軸や扁額として収蔵されています。
古くより蔵で受け継がれたものや遺品の相続などで、作者などもわからないというような場合でもご相談ください。
また掛け軸以外にも、古い骨董品などございましたら買取可能です。下記のページもご参考ください。
岡山の骨董品買取について
岡山県での掛け軸の買取実績
岡山で買取りさせていただきました掛け軸をご紹介します。
※骨董品・古美術品の性質上、全くの同一作品というものはなく、真贋はもちろんのこと状態や出来、その時折々の人気など様々な要素によって骨董品や美術品の価値・価格は変化します。
また、それらの要素を豊富な経験や実績、昨今のデータと照らし合わせて、お客様の品物一つ一つを適切に買取査定するのが私どもの役目でもあります。
買取事例の一つとして、あくまで参考価格とお捉えください。
岡山の掛軸出張買取対応エリア
-
備前
-
備中
-
美作
岡山全域で掛け軸の出張買取対応しております。買取が成立しなかった場合にも、出張費用等を請求することはございませんのでご安心下さい。また、当館の車に店名等は記載されておりません。秘密は厳守してプライバシーに配慮したお取引を心がけております。
遠方でもご遠慮なくお申し付けください。(お話の内容によりましては、お伺いできない場合もございます。ご了承ください。)

掛け軸の買取の藝品館へお越しいただきありがとうございます。
大切な掛け軸、一点ものの掛け軸だからこそ、一点一点鑑定し、必要とされている次のお客様へお繋ぎするのが使命と考えております。
掛け軸は専門の美術商でないと鑑定が非常に難しく、伝来が重要な掛け軸は江戸時代からの古書籍、データベースを所有している当館だからこそできるご提案が多くあります。

掛け軸についてのご相談は藝品館へ、ぜひお気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせいただければ、パソコンからスマホから、フォームに沿って必要項目をご入力いただくだけで迅速に簡易査定させていただけます。
また当館からのご連絡方法は、お客さまのご都合で指定していただけます。
メールで無料お問い合わせ
電話受付時間 9:00 ~ 20:00
メールやLINEでの受付は24時間承っております。
買取・無料査定のご依頼から各種ご相談まで、お気軽にご連絡ください。
買取方法の詳細につきましては買取査定の流れをご参照ください。

LINEでの簡易お問い合わせも承っております。
所有者・購入時期・作者名・売却のご予定やご希望価格など、なるべくご依頼・ご相談の内容がわかりますような詳細を添えてお問い合わせください。
また査定業務等の都合により、ご返答にお時間を頂く場合もございます。
予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
 LINEでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ