児島虎次郎作品の買取について
藝品館では児島虎次郎作品の買取査定を行っております。
児島虎次郎の洋画、油絵などの絵画の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
児島虎次郎という人物
児島虎次郎 (こじまとらじろう 1881-1929) は明治から昭和期にかけて岡山で活躍した洋画家です。
1881年に現在の岡山県高梁市で生まれた児島虎次郎は、幼少期から絵画に興味を持ちましたが、家業の手伝いなどで絵画の修行は許されず、近所に住む洋画家らから少しの指導と東京画壇の情勢を教えられていたとされます。16歳頃の作品には絵の具も買えずペンキで描いた 井上こう肖像(模写) (高梁市成羽美術館蔵)が残っています。
1901年に家族を説得して上京し、翌年には東京美術学校に入学を果たします。学生として西洋画を黒田清輝や藤島武二などに学びました。入学後、倉敷市の実業家・大原家の奨学生に推薦され、帰郷の際に後に大原美術館を創設する大原孫三郎と会い、後援を得ました。学業では東京美術学校を2年も飛び級し、引き続き研究科に入り、画技の研鑽に努めました。
卒業後の1907年には東京府主催勧業博覧会美術展で、逆光表現の中に孤児院を描いた なさけの庭 (皇居三の丸尚蔵館蔵)を出展して1等を受賞し、画壇にデビューしました。
1908年に大原家から渡欧を持ちかけられた児島虎次郎は、フランスへと向かいます。最初はパリの教室に通うとしていましたが、田舎のグレー村に移り、アメリカ人画家らと親交を結んでいます。
1909年からはベルギーに赴き、3年間滞在しています。ゲント王立美術アカデミーに入学し、絵画研究を重ねています。このアカデミーを1912年に首席で卒業しました。
1912年に帰国し、早速 酒津の農夫 (高梁市成羽美術館蔵)などの作品を描いています。その後数年間、中国や朝鮮に渡り、東洋的な画題を求めて多くの旅をします。風土や画材の違いに悩みスランプもあったようですが、居住した酒津周辺をモチーフとした数々の作品を残しています。1918年には画題や作品収集を目的に中国へ渡航した際、中国最後の文人と呼ばれる書画家・篆刻家である呉昌碩に出会い、深く傾倒して、中国を題材に墨彩画など様々な絵画を描きました。また呉昌碩には篆刻の制作依頼をするなど親しく交流を持ちました。
1919年に大原孫三郎の支援があり、絵画の研鑽だけでなく、孫三郎の本物の西洋画を日本に招来したいという思いから、絵画の収集役としても渡欧します。クロード・モネなどには実際に会いにゆき、 睡蓮 の作品購入に成功しています。またマティスからは画家の娘 を購入しています。1922年には再々渡欧し、エル・グレコの 受胎告知 を購入しました。他にもロダンやセガンティーニ、ゴーギャンなど大家の絵画を収集しています。またエジプトにも立ち寄り、陶器や彫刻などを購入しています。これら虎次郎が収集した品は、大原美術館の収蔵品の核となっています。
1921年に虎次郎は明治神宮奉賛会から、対露宣戦御前会議 (聖徳記念絵画館蔵)の壁画制作を依頼されました。この作品は3年かけて関係者に取材、アトリエの改装を行うなど、入念な準備をして制作され始めましたが、虎次郎は完成を見ることなくこの世を去りました。この 対露宣戦御前会議 は未完となりましたが、友人の画家・吉田苞の手によって完成しました。
児島虎次郎の画風
東京美術学校在学中の作品は黒田清輝の影響か、外光派風の柔らかな光とタッチで 里の水車 (大原美術館蔵)などの作品を描いています。
ヨーロッパで学んでいた時期、ヨーロッパでは後期印象派の影響が残り、マティスなどの野獣派と呼ばれるフォービズムの画家たちが活動していました。虎次郎の渡欧後の作品は印象派風であり、渡欧から帰国した時期には、エミール・クラウスに学んだ点描調で明るい作風の 酒津の農夫 和服を着たベルギーの少女 (大原美術館蔵)などを制作しています。1920年代の3度目の渡欧頃からはフォービズムの作風に傾倒し、荒々しいタッチと色彩で制作を行っています。赤と緑、青と黄などの補色の関係性を慎重に使用した、インパクトのある人物画 自画像 (大原美術館蔵)や風景画 奈良公園 (大原美術館蔵)などの絵画を描きました。
大原美術館の設立に多大な貢献を行った人物として、大原美術館内には児島虎次郎記念館が存在し、多くの作品が展示されています。
また虎次郎の孫・児島塊太郎が館長を務める加計美術館では近年、日中書画篆刻芸術交流展が開催されました。現在も子孫同士の交流が続き、上海呉昌碩記念館の館長である呉昌碩のひ孫・呉越を招いて、両者の作品や子孫の作品、関連する作品を展示し、日中の芸術交流が行われました。
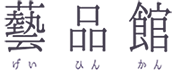

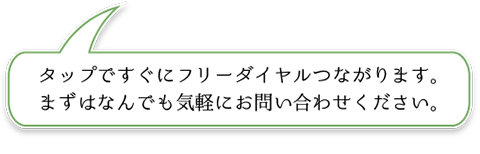
 LINEで
LINEで