金重素山作品の買取について
藝品館では金重素山作品の買取査定を行っております。
金重素山の備前焼、伊部焼の茶道具や陶磁器・陶芸作品等の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
金重素山という人物
金重素山 (かねしげそざん 1909-1995) は昭和から平成期にかけて岡山、京都で活躍した陶芸家です。
1909年に備前焼の金重楳陽の三男として岡山県備前市伊部に生まれた金重素山は、18歳の頃から13歳年の離れた長兄・金重陶陽の制作を手伝うようになり、焼物の道に入りました。陶陽は窯入れ、窯焚きなども素山に体験させて学ばせ、陶芸の道を示しました。
戦後は金重家が信仰していた 京都亀岡の大本教の神苑・天恩郷にて、花明山窯芸道場を築き、作陶を大本教三代・出口直日に教えるとと共に、同じく作陶指導をしていた後に人間国宝に指定される石黒宗麿に釉薬などの技法を学んでいます。そのためこの窯では李朝風や白化粧、赤絵、染付、鉄釉などの作品を焼いています。
また1960年には京都綾部市の大本教本部にある鶴山窯でも信楽や、灰釉、染付、天目などを宗麿と共に焼いています。大本教の窯では当時珍しかった電気釜が設置されており、のちの素山の作陶に影響を与えています。また大本教では芸術を重視したため、荒川豊蔵や北大路魯山人などの名工も訪れていました。
1964年に岡山市の丸山に築窯して独立し、ここで試行錯誤を繰り返すうちに火襷の模様が入った潤いのある焼物を電気釜で焼くことに成功しました。電気釜に少し薪を入れることで潤いと発色を成立させたとされます。
1984年には伊部に戻り、古備前の窯跡のある榧原山麓に、新たに登り窯の牛神下窯を作り、1995年に没するまで故郷での制作を続け、備前焼の復興と発展に力を尽くしました。
金重素山の作風
素山の作る陶器は重厚で厚みが少し足された、鷹揚とした雰囲気のあるものとなっています。茶碗などの茶陶から、徳利などの酒器、皿や椀などの食器などの日用雑器まで焼いています。
桃山風のおおらかなフォルムに、生地の発色や火襷の色合いも絶妙で固く締まった火襷作品が特に有名で数もありますが、他にも金彩や白化粧、信楽風の作品も制作しています。箱書きは備前焼と書かず、自身が生まれ、また備前焼発祥の地である伊部という土地を大切に思い、伊部焼と記す例があります。
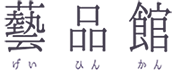

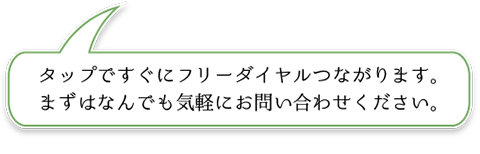
 LINEで
LINEで