小山冨士夫作品の買取について
藝品館では小山冨士夫作品の買取査定を行っております。
小山冨士夫の陶磁器等、陶芸作品のの売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
小山冨士夫という人物
小山冨士夫 (こやまふじお 1900-1975) は昭和期に活躍した岡山県出身の陶芸家、陶磁研究家です。
1900年に現在の倉敷市玉島に生まれた小山冨士夫は、東京商科大学に進学しますが中退し、25歳の時に、華族の岡田長世などの影響によって作陶に興味を持ちます。瀬戸の矢野陶々や京都の真清水蔵六に陶芸を学んで、京都東山にて作陶家を目指しました。
1930年頃には陶磁研究の志を持って再び上京し、陶磁研究家の奥田誠一に師事して古陶磁研究にも向かいます。また日本に留学中であった中国の歴史学者・郭沫若に出会い、中国を旅して1941年には宋代の定窯古窯址を発見しています。
戦後は東京国立博物館、文化財保護委員会の調査官として、多くの陶磁器に関する著作や評論を発表しました。代表的な著作は 東洋古陶磁 や 支那青磁史稿 などです。
1960年、加藤唐九郎の贋作による「永仁の壷事件」が発生します。壷の文化財指定の責任を取り、小山冨士夫は文化財保護委員の退任を余儀なくされました。
1964年からは再び作陶を開始。窯を神奈川県鎌倉市に永福窯や 岐阜県土岐市の五斗蒔街道に花ノ木窯を作り、作陶に励みました。その後も古陶磁の研究を行い、日本の六古窯の提唱、中国陶磁に関して故宮博物院で講演、東洋陶磁学会の常任委員長を務めるなど、研究家として多くの業績を残しています。
1964年頃からの晩年の作品が多く残り、研究者らしく全国様々な技法を用いて、唐津焼や伊賀焼、京焼、備前焼、また種子島の土を用いて能野焼を再現した作品を作っています。茶碗や建水、花入などの茶道具や、向付や椀などの食器、徳利やぐい呑などの酒器を制作しました。
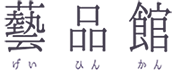

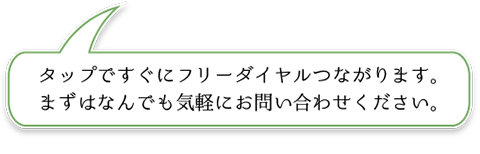
 LINEで
LINEで