竹久夢二作品の買取について
藝品館では竹久夢二作品の買取査定を行っております。
竹久夢二の日本画・絵画・掛軸・版画等の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
竹久夢二という人物
竹久夢二 (たけひさゆめじ 1884-1934) は明治から昭和期にかけて活躍した岡山出身の画家、詩人、デザイナーです。
別号やペンネームに幽冥路、さみせんぐさなど。
1884年に現在の瀬戸内市に生まれた竹久夢二は17歳で上京し、18歳で早稲田実業学校に入学。学業を行いながら、詩や飾り絵であるコマ絵を雑誌や新聞に投稿する生活を送り、新聞などに絵が掲載されることもありました。21歳で投稿したコマ絵 筒井筒 が第一賞入選し、この時初めて夢二の号を用いてます。1906年からは本の装丁や、口絵などを担当し始めます。
1907年の23歳の時、岸たまきと結婚し、たまきをモデルとして初期の「夢二式美人」が生まれています。また新聞にて幽冥路の名を使い絵や川柳を発表しています。
1909年の最初の著作 夢二画集 春の巻 を始めとして、画集、詩集など多くの著作物を刊行しています。また楽譜の装幀や絵葉書、日用雑貨のデザイン、広告なども手掛けました。これらの仕事によって1910年代からは夢二の絶頂期となっています。この頃には夢二を取り巻いた女性、彦乃やお葉が現れ、彦乃をモデルとして 夏姿 や吉井勇の著 祇園歌集 には彦乃を描いた表紙などを提供し、お葉をモデルとして、名作である黒猫を抱く女性を描いた 黒船屋 (竹久夢二伊香保記念館蔵)などを描き「夢二式美人」の完成に至りました。
1923年の39歳の時、自身の会社「どんたく図案社」を設立しますが、関東大震災に遭い壊滅し、新聞社にて「東京災難画信」を連載しています。翌年には東京世田谷にアトリエ兼自宅の少年山荘を建て、ここで活動を始めます。
1930年、「手による産業」によるデザインや絵画の普及を図って美術研究所の構想を練り、度々逗留していた榛名山を望む群馬の伊香保温泉にて、5月に「榛名山美術研究所建設につき」の宣言文を発表します。この宣言文には詩人や画家として活躍していた文化人の森口多里、島崎藤村、有島生馬、藤島武二などが名を連ねました。研究所が完成した暁には春の女神を描いた 榛名山賦 (竹久夢二伊香保記念館蔵)と秋の女神を描いた 立田姫 (夢二郷土美術館蔵)を対で飾るとしていたようです。
この後、数年かけて研究所の資金集めに奔走しますが、アメリカやドイツ、台湾を作品展のため巡ったのちに病にかかり、研究所の完成を見ることなく49歳で没しました。
現在、竹久夢二を顕彰するための美術館や記念館が多く建てられ、出身地である岡山には夢二郷土美術館が、東京には竹久夢二美術館が開館し、伊香保の地には竹久夢二伊香保記念館が建てられています。
竹久夢二の画風
竹久夢二は画家としては水彩・油彩を用いて日本画の技法や洋画の技法で作品制作を行い、デザイナーとしては日用雑貨のポチ袋や半襟、浴衣、挿絵、絵葉書、パッケージデザイン、本、楽譜の装幀、ポスターなどの制作を行っています。夢二は生活の全てに美術を取り入れた人物でした。
郷愁を帯びた独自の美人画「夢二式美人」を描いて、大正ロマンを代表する芸術家とされ、時には「大正の浮世絵師」とも呼ばれています。代表作の 立田姫 では夢二がミス・ニッポンと語った、豪華な赤の着物をまといながらも細身でS字のラインを描き、儚さを感じさせる表情をした女性像が作り上げられています。他の美人画もどこか憂いを帯びた美人達が並びます。
夢二の人気は、生活用品に可愛さや楽しさを出した生活雑貨等が支えていました。榛名山美術研究所の宣言にあたっても産業と芸術の一体化を図ろうとしており、生活の中に根ざした芸術の創作に最後まで心を砕いていたようです。
現在においても竹久夢二の作品は大正ロマンの代表作家として非常に人気があり、様々な出版物が刊行され、雑貨などが再販やリメイクされて販売されることもあります。
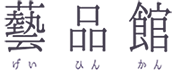

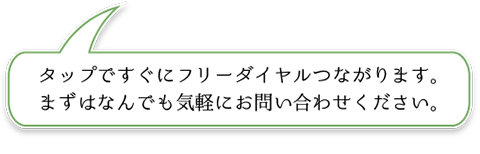
 LINEで
LINEで