古銭の買取について
藝品館では、多岐にわたる種類の古銭を積極的に買取しております。
お客様がお持ちの古銭一つ一つに対し、経験豊富な鑑定士がその状態(傷、汚れ、サビの有無など)や、専門的な知識と最新の鑑識技術を駆使して真贋を丁寧に鑑定・査定し、市場価値に基づいた適正価格で、お客様にご納得いただける買取価格をご提示いたします。
趣味の収集は数多くありますが、近年、古銭コレクターが急速に増加しています。その理由として国際的に金・銀の価格が高騰し、古銭の希少価値に目を付け投機的に収集しようとする人が増えたことが挙げられます。
古銭は、先祖から受け継がれた貴重な文化遺産であり、その一枚一枚が歴史的背景を現代に伝えてくれるものです。埋もれた価値ある古銭の発見をお手伝いし、次の世代へと受け継ぐ架け橋となることを目指しておりますので、ぜひ一度、藝品館にご相談ください。
古銭の種類
金貨
金貨は明治3年から発行され、日本では冠婚葬祭など様々な場面で重要な役割を果たしてきました。
明治3年の金貨は発行枚数が46,139枚と希少性が高く、その後も少ない状態が続きます。旧10円金貨には有輪のものと無輪のものがあり、区別が必要です。
- 旧20円金貨
- 旧10円金貨
- 旧5円金貨
- 旧2円金貨
- 旧1円金貨
- 新20円金貨
- 新10円金貨
- 新5円金貨
銀貨
銀貨は彫刻的な美しさから多くの収集家を魅了しています。
1円銀貨は貿易用として使用されたほか、貿易銀や、中国の両替商が判別のため押した極印が施されたものなど、多種多様な種類が存在します。また龍の紋様や文字、その他の紋様の違いなども多くあり、収集家の間で高い人気を誇ります。帝室技芸員がデザインしたものなど、海外の貨幣コインと比較してもデザイン性や彫金技術が注目され、高い評価を得ているものも多くございます。
- 旧1円銀貨
- 旧1円銀貨丸銀打
- 新1円銀貨(大型)
- 新1円銀貨(小型)
- 新1円銀貨(大型)丸銀打
- 新1円銀貨(小型)丸銀打
- 貿易銀
- 貿易銀丸銀打
- 旭日竜大型50銭銀貨
- 旭日竜小型50銭銀貨
- 50銭銀貨
- 旭日50銭銀貨
- 八咫烏50銭銀貨
- 小型50銭銀貨
- 旭日竜20銭銀貨
- 竜20銭銀貨
- 旭日20銭銀貨
- 旭日竜10銭銀貨
- 竜10銭銀貨
- 旭日10銭銀貨
- 八咫烏10銭銀貨
- 旭日竜5銭銀貨
- 旭日大字5銭銀貨
- 竜5銭銀貨
古金銀
古金銀は大判小判はなどの代表的な古銭としての位置付けのものです。
製造された時代によって時代によって材料の配分が異なるのも、歴史的背景があり見所があります。
大判
大判は安土桃山時代・江戸時代の金貨幣の一種です。
大判はもともと板のようにつくり「バン金」(板金・判金・版金)などと呼ばれていました。大判と名付けられたのは、小判に対して大判と呼び、成立時代は室町中期と伝えられています。
豊臣秀吉が鋳造させた天正大判が有名で、形も楕円となり桐紋の極印が打印され「拾両後藤」と花押(かおう)が墨書きされ、量目165グラムとなりました。しかしこの大判は一般流通の通貨としてではなく、贈答等の目的に使われていたようです。
江戸時代にはこの天正大判に倣って、五種類ほど鋳造されたと伝えられています。
天正大判に倣った最初の大判は、徳川家康が鋳造した「慶長大判」です。これは元禄8年(1695年)まで続けられ、「元禄大判」「享保大判」「天保大判」「万延大判」が作られました。
こうした大判は、幕府の御用彫金家後藤家の大判座で造られ、時代により品質の優劣はあったと伝えられています。
- 天正菱大判金
- 天正長大判金
- 天正大判金
- 慶長笹書大判金
- 慶長大判金
- 慶長大判金(明暦判)
- 元禄大判金
- 享保大判金
- 天保大判金
- 万延大判金(たがね打)
- 万延大判金(のし目打)
小判
小判は江戸時代の金貨幣の一種です。大判を小型化したもので、一枚で一両を基本とする金貨幣の基準となるものです。
徳川家康が江戸時代駿河で鋳造させましたが、天下平定の後、1601年(慶長6年)金座に慶長小判を鋳造させ全国に流通させました。その後元禄・宝永・享保・元文・文政・天保・万延などで数多くの小判が発行されています。
徳川家康のように全国統一の物ではないが、この時代多くの小判が作られました。上杉謙信・武田信玄・織田信長・今川義元・伊達正宗・北条氏康などの大名たちです。こうした戦国武将の小判は、品質も一定しないものが多く作られました。
- 慶長小判金(江戸・京・駿河座)
- 元禄小判金
- 宝永小判金(乾字小判)
- 正徳小判金
- 享保小判金
- 佐渡小判金(佐字小判)
- 元文小判金(真文小判)
- 文政小判金(草文小判)
- 天保小判金(保字小判)
- 安政小判金(正字小判)
- 万延小判金(雛小判)
その他の古金銀
- 天保五両判金
- 円歩金(太閤円歩金)
- 文政二分判金
- 文政二分判金
- 安政二分判金
- 万延二分判金
- 明治二分判金
- 額二分判金
- 慶長一分判金
- 元禄一分判金
- 宝永一分判金
- 正徳一分判金
- 享保一分判金
- 佐渡一分判金
- 元文一分判金
- 文政一分判金
- 天保一分判金
- 安政一分判金
- 万延一分判金
- 元禄二朱判金
- 天保二朱判金
- 万延二朱判金
- 文政一朱判金
- 明和五匁銀
- 古南鐐二朱銀
- 新南鐐二朱銀
- 文政南鐐一朱銀
- 天保一分銀
- 庄内一分銀
- 安政一分銀
- 嘉永一朱銀
- 明治一分銀
- 明治一朱銀
- 安政二朱銀
- 改三分定銀
丁銀・豆板銀
丁銀・豆板銀には秤量貨幣と定位貨幣があります。丁銀は取引の都度重量をはかって使用した為秤量貨幣となります。元和以降は端数計算をやりやすいように豆板銀が作られます。
豆板銀も大黒の極印以外に打ち方や紋様は色々あり見所があります。
古丁銀類
- 萩古丁銀
- 御公用丁銀
- 文禄石州丁銀
- 天又一丁銀
- 括袴丁銀
- 博多御公用丁銀
- 慶長丁銀・豆板銀
- 元禄丁銀・豆板銀
- 宝永二ツ宝丁銀
- 宝永永字丁銀
- 宝永三ツ宝丁銀
- 宝永四ツ宝丁銀
- 正徳・享保丁銀
- 元文丁銀
- 文政丁銀
- 天保丁銀
- 安政丁銀
地方貨
- 筑前分金
- 秋田九匁二分銀判
- 秋田四匁六分銀判
- 盛岡八匁銀判
- 美作銀一分
- 但馬南鐐銀
- 加賀南鐐銀
- 秋田笹一分銀
- 秋田封銀
- 会津銀判
- 仙台小槌銀
- 出羽角館印切銀
- 越後寛字印切銀
- 佐渡徳通印切銀
- 出羽窪田印切銀
- 甲州露一両金
- 古甲金石目打
- 甲州一分金
- 甲州二朱金
- 甲州一朱金
- 甲州朱中金
穴銭
皇朝十二銭
- 古和同(銅)
- 古和同(銀)
- 和同開珎
- 萬年通宝
- 神功開宝
- 隆平永宝
- 富壽神宝
- 承和昌宝
- 長年大宝
- 饒益神宝
- 貞観永宝
- 寛平大宝
- 延喜通宝
- 卓元通宝
桃山時代の穴銭
- 天正通宝
- 文禄通宝
- 紹聖元宝
- 永楽通宝
江戸時代の穴銭
- 慶長通宝
- 元和通宝
鐚銭・加治木銭
- 洪武通宝
- 祥符通宝
- 平安通宝
- 元祐通宝
- 治平元宝
- 景徳元宝
- 元豊通宝
- 元通通宝
- 天聖元宝
- 元符通宝
- 元豊通宝
- 唐国通宝
- 熙寧元宝
長崎貿易銭
- 元豊通宝
- 嘉祐通宝
- 熙寧元宝
- 祥符元宝
- 紹聖元宝
- 天聖元宝
寛永通宝
寛永通宝は同じように見えるものが多いですが、よく見ると字体や材質が異なり、収集するには面白いものです。字体や作られた場所でも大きく値段が変わる場合があるので注意が必要です。
- 二水永(水戸)
- 芝銭
- 浅草銭
- 坂本銭
- 水戸銭
- 仙台銭
- 吉田銭
- 松本銭
- 高田銭
- 岡山銭
- 長門銭
- 竹田銭
- 岡山銭
- 建仁寺銭
- 沓谷銭
- 鳥越銭
新寛永
- 島屋文
- 島屋文(無背)
- 正字文
- 正字入文
- 退点文
- 萩原銭
- 四ツ宝銭
- 耳白銭
- 丸屋銭
- 日光御用銭
- 正徳期
- 享保期
- 広穿背左
その他の古銭
- 絵銭
- 近代貨幣
- 現行貨幣
- 記念貨幣
- 軍用貨幣
- 地方自治記念貨幣
- 貨幣セット
- 幕府政府及び府県札類
- 近代紙幣
- 軍用手票類
- 在日米軍軍票
- 在外銀行券類
- 在外貨幣類
古銭の買取実績
買取りさせていただきました古銭をご紹介します。
-

竜五十銭銀貨などの古銭買取
買取品目:古銭
買取作品:竜五十銭・竜二十銭銀貨など
買取エリア:京都市左京区買取参考価格 220,000円
-

一分銀や小判など古銭の買取
買取品目:古銭
買取作品:一分銀 小判など
買取エリア:名古屋市港区買取参考価格 450,000円
※骨董品・古美術品の性質上、全くの同一作品というものはなく、真贋はもちろんのこと状態や出来、その時折々の人気など様々な要素によって骨董品や美術品の価値・価格は変化します。
また、それらの要素を豊富な経験や実績、昨今のデータと照らし合わせて、お客様の品物一つ一つを適切に買取査定するのが私どもの役目でもあります。
買取事例の一つとして、あくまで参考価格とお捉えください。
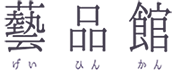

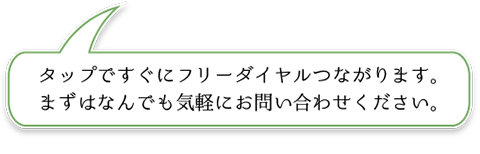








 LINEで
LINEで