池田遙邨作品の買取について
藝品館では池田遙邨作品の買取査定を行っております。
池田遙邨の日本画・絵画・掛軸・屏風等の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
池田遙邨という人物
池田遙邨 (いけだようそん 1895-1988) は大正から昭和期に活躍した日本画家です。
1895年に現在の岡山県倉敷市に生まれた池田遙邨は幼い頃より絵が得意であり、1910年の15歳の頃、大阪に出て同じく岡山の洋画家・松原三五郎の天彩画塾でデッサンや油絵の教えを受けました。
天彩画塾は入門から2年ほどで脱会していますが、1913年に岡山で初の個展を開きます。その際、日本画家・竹内栖鳳の門人であった同じ岡山県出身の 小野竹喬に出会いました。これはのちに日本画への転向するに至る、運命的な出会いとなりました。
1914年に19歳で文展に広島の鞆の浦を描いた水彩画 みなとの曇り空 を出展し、初入選しました。若干19歳での入選は周囲を驚かせました。
2年間の兵役後、1918年の文展に農夫を描いた日本画作品 草取り を出展し落選しますが、遙邨自身はこれを洋画からの決別と評しています。その後の1919年には小野竹喬を頼って京都に出て、竹内栖鳳の画塾・竹杖会に入門します。竹杖会に入門したその年に帝展にて 南郷の八月 が入選し日本画家として再スタートしました。
1921年には竹杖会以外にも京都市立絵画専門学校にも通い、1924年に卒業。一時岡山に帰って寺院などで絵画の修行をしますが、京都に戻り絵画専門学校の研究科に進学し、この頃、号を遙邨としています。
1928年に 雪の大阪 (大阪中之島美術館蔵)を帝展に出展し特選、1930年には岡山城を描いた 烏城 で特選を重ねました。
歌川広重に傾倒し、1931年頃には20日かけて東海道を歩き、浮世絵風の日本画作品 昭和東海道五十三次 を完成させています。
戦後は一時期 戦後の大阪 (大阪中之島美術館蔵)のような抽象的、記号的な作品も描きましたが、動物や自然をデフォルメして描いた作品が増え、特に 幻想の明神礁 (倉敷市立美術館蔵) 嵐山薫風 (福田美術館蔵)など風景画において、その装飾性は一つの境地に至っています。
晩年には明治の俳人・種田山頭火に感銘をうけ、山頭火の姿を模倣した格好で旅をし、その句を絵にした山頭火シリーズなどを手掛けました。
池田遙邨の画風
画業の初期の池田遙邨はスケッチやデッサンに基づく、油彩画や水彩画を制作していますが、小野竹喬の助言により、日本画家を志します。師である竹内栖鳳と同様に西洋画も取り入れ、情緒的な日本画を模索しました。
日本画を学び始めた後もムンクやフランシスコ・デ・ゴヤなどの西洋画家の影響を受け、人の儚さを描く 災禍の跡 を制作するなど洋画の影響が抜けきっていません。しかし、古くからの憧れである歌川広重の影響から浮世絵の構図を模した作品も描くようになり、1931年には58枚に及ぶ大作 昭和東海道五十三次 を浮世絵風日本画にて描いています。
戦後には記号で大阪の惨状を描いた 戦後の大阪 などの抽象画から幻想的な作風へ移行し、特に 幻想の明神礁 などに見られる、現実世界にはない幻想的な彩色の世界観の、コミカルとも取れるようなユーモアのある画風が広がります。また1950年代なかばにはトレードマークとされる狐や狸、梟などの動物を描くことにも力を注いでいます。
晩年には種田山頭火に心を傾け、山頭火の句を洒脱で澄んだ画風の絵画に落とし込んでいます。 行きくれてなんとここらの水のうまさは 山頭火 (倉敷市立美術館蔵)などの山頭火シリーズは、山頭火の句が遙邨の幻想感漂う細やかな絵で表される静謐なものとなっています。
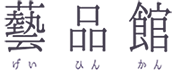

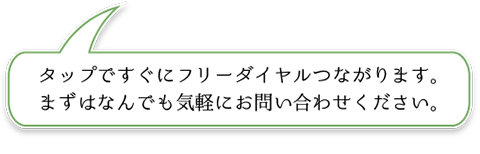
 LINEで
LINEで