犬養毅/木堂作品の買取について
藝品館では犬養毅作品の買取査定を行っております。
犬養毅の書画・掛軸・扁額・屏風等の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
犬養毅という人物
犬養毅/木堂 (いぬかいつよし/ぼくどう 1855-1932) は明治から昭和期に岡山、東京で活躍した政治家です。
号は木堂のほか木翁、白林遯叟など。
1855年に現在の岡山県岡山市で大庄屋の家に生まれた犬養毅は、5歳頃から漢学を修め優れた能力を発揮しました。1872年には東京へ出るために県庁で働き、そこで現在の国際法に当たる萬国公法に触れて洋学を学びたいと思うようになります。
1875年に20歳で上京し、共慣義塾に入学、翌年には慶應義塾に転塾し福沢諭吉に学んでいます。生活のため新聞社に寄稿しながら学業に勤しんでいました。1877年に一時休学し、西南戦争の戦場に飛び込み現地のルポルタージュを出します。そのルポの文章が名文であったため名声を得ています。
新聞社を立ち上げるなど、記者としてのキャリアを積みますが、1881年に東京府会議員に当選し政治家となります。1882年の立憲改進党の結成に始まり、多くの政治的グループの立ち上げに尽力しました。1890年には第一回衆議院選挙で当選し、以後没するまで議員に当選を続けました。また中国や朝鮮、ベトナムの革命家や政治家らと交流を持ち支援をしています。
1925年に日本で普通選挙が始まると政界を引退すると表明しますが、岡山の支援者たちがそれを許さず、議員を続けることとなります。1931年には満州事変などで政治不安のある中、総理大臣に就任、議員の規律の引き締めなどを行いますが、1932年の5月15日に海軍青年将校の凶弾に倒れました。
犬養毅の書風
犬養毅は漢籍を学んでいた文人・犬養木堂として多くの書を残しています。書のスタイルは名人を真似ても仕方がないので、古人と自分を3対7くらいで落とし込むとしています。
実際、古筆の黄庭堅や 米芾に学んだ様子も見られますが、自分の個性を出し、漢字は少し角ばって早いリズムで書かれたものが見られ、かなでは芯がありながらも短く線を流しています。
また落款に使用された印には中国の書画家・篆刻家である呉昌碩に篆刻を依頼したものがあり、木堂は終生この印を使用していたようです。
志半ばに倒れた政治家、文人として、現在も非常に人気のある人物です。
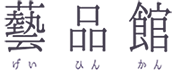

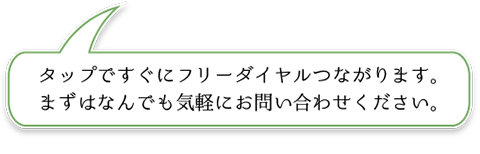
 LINEで
LINEで