雪舟等楊作品の買取について
藝品館では雪舟等楊作品の買取査定を行っております。
雪舟等楊の日本画・絵画・掛軸・屏風等の売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
雪舟等楊という人物
雪舟等楊 (せっしゅうとうよう 1420-1506) は備中国(岡山県)生まれの室町時代に活躍した禅僧で、中国から伝来した水墨画の技法を習得して山水画を大成させた日本美術史を代表する画家の一人です。
主に号である雪舟の名で知られ、諱を等楊といいます。
現在の総社市赤浜に武家の子として生まれた雪舟は幼少の頃に宝福寺に入ったのち、10歳頃に京都の臨済宗の大本山である相国寺に入ることを許されました。
禅の修行とともに当時山水画で名を上げ、足利将軍家の御用絵師となっていた周文に絵画を学び、宋元画の夏珪や馬遠などの要素を持つ絵画を学んだと見られます。
1450年代半ばごろより周防国(現在の山口県大内氏の庇護を受け、山口市)に画房「雲谷庵」を開設したのち、さらに明(中国)に渡るなどして宋元画を広く学び、絵画に関する知識と視野を広げます。その成果は夏珪や李唐などの数々の倣古図に表れています。その後、大分に「天開図画楼」を開き創作活動に励みました。
その生涯には謎が多く、のちに大きな影響を与えることになった狩野派から火が付いた絶大な人気によって、雪舟の逸話には後世による創作も含まれております。また近年では同一人物であったとの見方が強い拙宗等揚との関連性についても、時代により大きく意見のわかれるところでした。
晩年に過ごしたといわれる島根県 益田市にはゆかりの地や作品を多く残しています。
室町時代末頃より、山水長巻を所持する雲谷派を筆頭に、狩野派、長谷川派などの画壇を制した流派が、雪舟を祖師と崇めるようになり、深く自然を観察して描く水墨山水画様式は、その筆使い、構図、画題、余白など多くの面で日本の絵画に影響を与えることとなりました。代表作品として天橋立図・四季山水図(山水長巻)・富士三保清見寺図などがあります。
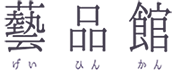

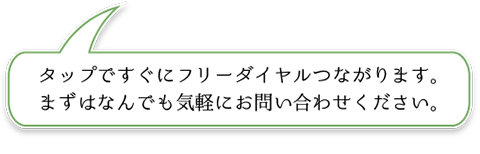
 LINEで
LINEで