逸見東洋作品の買取について
藝品館では逸見東洋作品の買取査定を行っております。
逸見東洋の 刀剣・木彫、竹彫、漆芸などの彫刻作品・書画などの売却や鑑定をお考えの際は、是非お気軽に当館へご相談ください。責任ある評価・査定を行い、現在の流通価格に沿った適切な買取価格をご提示いたします。
逸見東洋という人物
逸見東洋 (へんみとうよう 1902-1984) は幕末から大正期にかけて活躍した岡山出身の刀工であり木彫、竹彫、漆芸の工芸家です。
号は東洋の他、逸東洋、象谷、臥乕、鍔東洋、黄薇東洋、呑象、呑象逸人。他に刀工として竹貫斎義隆(竹貫斎源義隆)の号を持ちます。
1846年に現在の岡山県岡山市竹屋という刀剣商の家に生まれた逸見東洋は、幼少期から手先が器用で、10歳ごろには根付師の出目上満の根付を真似して彫っては売りに行き、寺子屋を抜け出しては箕之祐という絵馬師の所に入り浸って絵や字を学なび、宿札などを書いて評判を得ていたようです。また12歳にして岡山藩家老・伊木三猿斎に目通りし、木彫の「鬼面」が褒められ、更に目貫の注文まで受けました。
16歳の頃には京都の刀工・尾崎源五右衛門助隆に師事して指導を受けています。3年後、岡山に戻って刀工竹貫斎義隆(竹貫斎源義隆)として活動を始めます。この頃の岡山は幕末の動乱で殺気立ち、東洋の作刀した刀剣はよく売れたとされています。
明治に入ってからは更に名が上がり「明治政宗」とも呼ばれましたが、1871年の散髪脱刀令によって廃業せざるを得ませんでした。1871年、最後の大仕事として倉敷市の羽黒神社に刀身、双竜の彫物、研ぎ、刀装具の制作に至るまで、全て自身で行った 大太刀「銘 備前国岡山住逸見竹貫斎源義隆二六才刳物同作/備中国甕江郷社於羽黒大神御前謹作之 明治四年冬十一月吉日」 を奉納しました。
ここよりしばらく、岡山の金工家・正阿弥勝義の家で彫金などを真似て遊んだり、手伝いなどをして生活しています。勝義がよく題材とし、東洋もしばしば制作した丸みのある虫などの図柄に影響を見ることが出来ます。また公家出身の木彫家・諏訪五郎の弟子ともなっています。26歳頃には南画家の藤田石雲や、田能村直入などと北陸まで旅行し、3年遊歴しました。
その後、これまでの学びを活かして、木彫や竹彫などを行い、刀工として培った鋭い切れ味の道具で高い技巧の作品を数多く制作しました。特に第4回内国勧業博覧会に出品された動く仕掛けのされた蟹の作品は1等賞を得ています。また漆芸において他の追随を許さないほどの技術を示し、岡山名産の備中漆をもって堆朱、堆黒の他、堆白、堆黄、堆紫など様々な色の漆に彫刻を行い、細密な作品を制作しました。漆芸の作品においても展覧会で多くの賞を受けています。また正阿弥勝義や加納夏雄、海野勝珉らと大衝立を3年掛かりで共同制作し、漆芸部分を担当しています。
また作刀も廃刀令以降にも何度か行っており、1885年の明治天皇行幸の際、梅を抱えた龍の高肉彫りがほどこされた刀は天覧に預かって献上となります。その後犬養木堂の語るところではその刀は明治天皇の差料となったと伝わります。
逸見東洋の作風
逸見東洋の木彫ではケヤキや紫檀、ホオノキ、松などを使用し、飾りをほどこした根付、鞘、座卓、茶盆、煙草入、箱などを作り、茶道を趣味としたためか竹彫では茶合、茶杓などの茶道具も数多く制作しています。どのような作品であっても木目や筋を感じさせない切れ味の鋭く深い彫りが行われています。
また逸見東洋で至高とされるのは漆芸作品であり、何百回と漆を塗り重ねては色を調整し、漆に厚みが出たところで、細やかな文様を彫刻する超絶技巧の作品が知られています。
代表作は6年かけて制作された最高傑作 風神雷神図堆朱盆(林原美術館蔵)です。単色に見えますが少しずつ黄漆などを混ぜて漆の層に表情を持たせ、そこに細く筋を入れるように図様や下地の文様を刻み込んでいます。図は巨勢金岡の風神雷神を元としたとされますが、周りを取り巻く麒麟や龍などの霊獣は、東洋自らが下絵を作成した物となっています。漆芸作品は深く艶のある作品が多く、香合などの小品にも異才の腕が見て取れます。
刀剣の逸見竹貫斎作品も作刀期間は短いものの残されており、新々刀とは思えないほどの古刀の風格が備わった作品となっています。また刀身の彫物や銘なども見事な彫りがなされる作品があります。
書や絵画も行い、宿札や 山間激流図 などの作品を残しています。
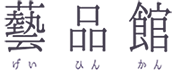

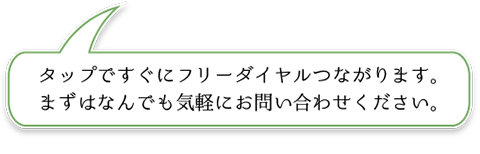
 LINEで
LINEで